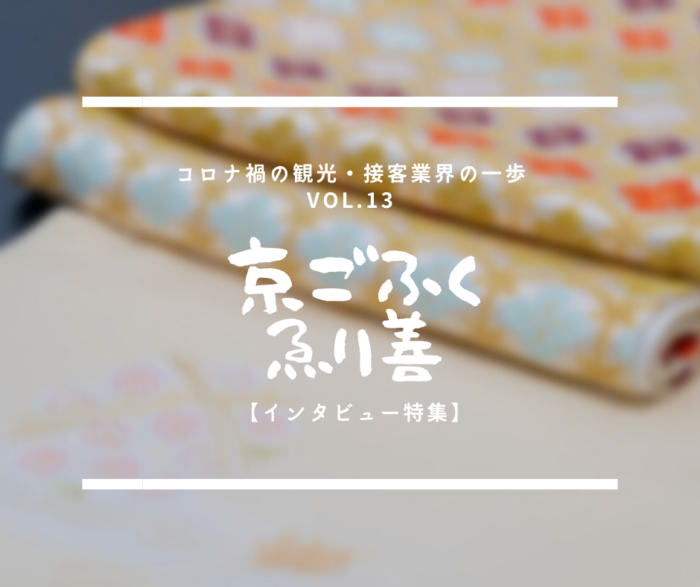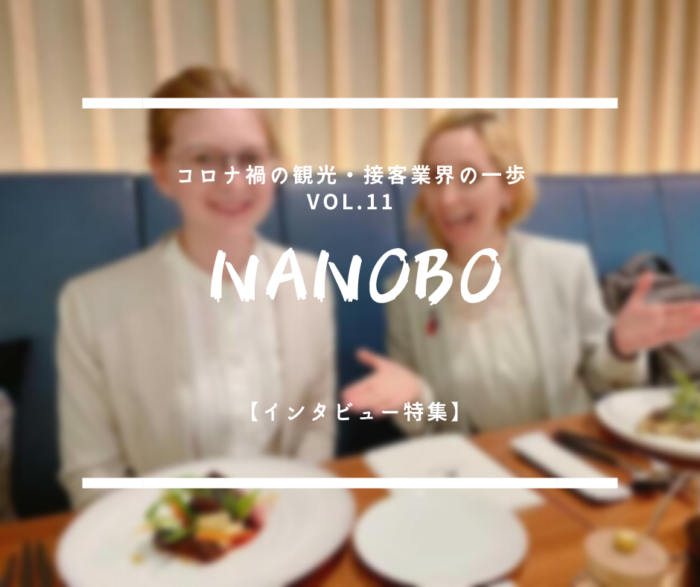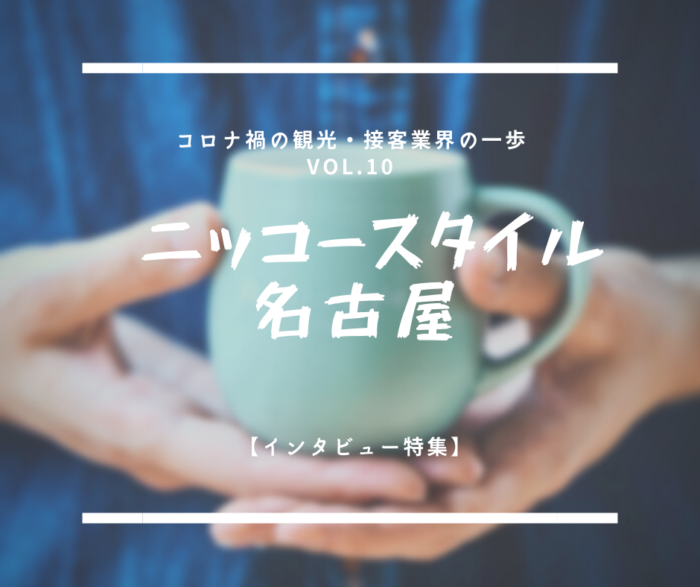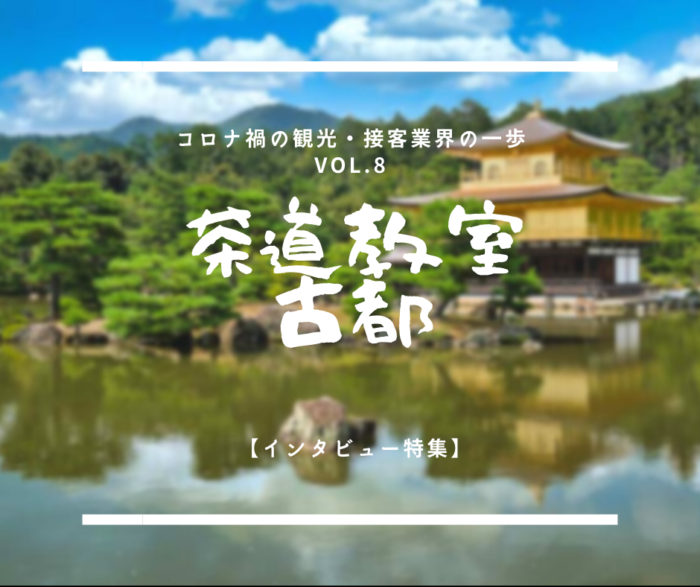①インバウンドとは
・インバウンドの経緯

インバウンドとは直訳で言えば「外から内へ」という意味で、旅行会社の業界用語として「インバウンド観光」と言われていました。
それが2009年に観光庁が外国人観光客を増やすアクションプランを策定したことをきっかけに、「インバウンド観光」という言葉が一般にも頻繁に使われるようになり、訪日外国人観光客の総称として「インバウンド」、という言い方が定着したというのが私の認識です。
2009年当時のインバウンドの目標数値は2020年に2000万人でしたが、これは2015年に1973万人という形で5年前倒しで達成しています。 そして、アドリンクでは2013年から訪日外国人向けのサービスを構想し、2014年に京都市交通局協力のもと、訪日外国人向けの通訳タブレットのレンタルサービスを開始しました。(※2016年サービス終了)それをきっかけとし、現在に至るまで、通訳、翻訳、外国語でのコンテンツ制作、訪日外国人のニーズ調査など様々なアプローチで外国人観光客の受け入れをしたい企業様や自治体のサポートを実施してきました。
②インバンドの現状
・オーバーツーリズムによる満足度の低下

2020年の政府目標であるインバウンド4000万人はほぼ確実に達成すると言われていますが、現状について整理してみます。
これまでは東京、大阪、京都など、新幹線が繋がっているいわゆるゴールデンルートが訪日観光の中心だったわけですが、現場に目を向けると様々な地域に外国人観光客が訪れるようになっています。
そんな中、僕たちが拠点を置く京都では元々観光都市である中でさらに外国人観光客が急増していることもあり、「オーバーツーリズム」と言われるような課題も出てきています。 外国人観光客が増えることによって、確かに観光消費額は2030年には日本の今の自動車の輸出額に匹敵するような一大産業になることは間違いないです。(※2030年の訪日外国人による観光消費額は15兆円に到達すると言われていますが、現状の推移で達成されるかどうかは不明)
しかし、その反面で地元住民との共存や観光の満足度が失われていく、風情が失われていく、という点も課題と言えるでしょう。
例えば中国人観光客の爆買いを意識した結果、京都の至るところに中国語の看板がある状況は京都っぽさ、日本っぽさが失われているという事例があげられます。 京都の観光課題を例にお話しましたが、一方でお隣の奈良県では外国人観光客の訪問率の高さに反比例して観光消費額は全国最下位になることもあり、京都・大阪の“ついで観光”からの脱却が当面の課題になっています。
外国人観光客が増えることによって日本の観光産業が盛り上がっていく、一方で地域によってそれぞれの課題、問題というのも同時に出てきているというのが日本のインバウンド観光の現状だと思っています
③これからのインバウンド
・これからの受け入れ

受け入れの現状によって課題も変わりますし、対策も変わってくると思います。
それぞれの地域、それぞれの課題に合わせたソリューションをアドリンクは提案、提供しているわけですが、前述の通り、例えば京都ではオーバーツーリズムによる、観光満足度の低下が叫ばれる中、観光客をいかに京都市内の中でも限られた場所だけではなく、府域に分散することで改善しようという話があります。
また、観光客の受け入れの総量規制をするというアプローチもあります。例えばオランダのアムステルダムでは京都と同じようにオーバーツーリズムが深刻な観光課題になり、観光客の総量規制と分散を組み合わせた対策を行っている事例もあります。
京都でも限られたキャパシティーの中で一つの方法として総量規制による京都としてのブランド価値を向上させ、平均宿泊数の増加や観光消費額の単価増を目指していくというのもアリだと思っています。
・これからの観光消費

訪日外国人の観光消費額は2018年に4兆5000億円、2030年には15兆円に到達すると言われています。
一方訪日外国人の数は2018年時点で約3119万人、2030年には6000万人、つまり訪日外国人の数が2倍に増加する見込みに対して観光消費額は3倍になる見込みになると言われています。 ここまで観光消費額が順調に増加した背景にはもちろん訪日外国人数の増加もあるのですが、やはり中国人観光客を中心とした爆買いは大きな要因だと言えます。
しかし、これからの観光消費ではショッピングに期待するのは難しいと考えています。 訪日外国人に向けた観光庁のアンケートには、「今回の訪日時にしたこと」「次回訪日時にしたいこと」という項目があります。 今回したことにショッピングを上げた人は約80%に上りますが、次回したいことでショッピングを上げた人は約40%に留まります。(参考:訪日外国人の消費動向調査結果及び分析平成28年10-12月期報告書) ここまで急激に増加した訪日外国人が今後リピーターとして訪日することも多くなることを考えると爆買いへの期待は長期的に考えることは難しくなることが考えられます。
そこでショッピングによる観光消費、いわゆるモノ消費だけに期待するのではなく、まだまだ増加の可能性が大いにある体験などをメインにしたコト消費(娯楽サービス費)に焦点を当てることが2030年の15兆円の観光消費額達成の一つのキーになります。
・これからの誘客

実際にその可能性を感じた出来事をお伝えしたいと思います。
先日、滋賀県彦根市で外国人観光客を招いた稲刈り体験ツアーのサポートをさせて頂きました。彦根市というと彦根城が有名ですが、そのツアーは中心街ではなく、中心街から車を走らせて向かわないといけない農村での実施でした。 内容は参加者に稲刈り等の農業体験をして頂き、自分達で刈ったそのお米でおにぎりを作って地元の方たちと一緒に食事をするというシンプルな体験でしたが、終了後のアンケート調査では満足度が高く、参加者の中には予定を変更して彦根に宿泊する方や、訪日観光の中で一番楽しかった体験でした、と言ってくれた方もいました。
単にその地域のことを海外にPRするだけではなく、“そこに来てもらう理由を作る”“そこに来るために日本に来る”という状況を作り出すことが外国人観光客にとってアクセスの悪い地方への誘客の大きなヒントになる事例だと思いました。
まとめ

2020年の東京オリンピックを控え、これから更に盛り上がっていくインバウンド観光。 数年前からインバウンド観光はいつか下火になると危惧されていますが、増加率は落ち着きを見せるものの、日本の観光産業にとってなくてはならない存在になっていると考えます。
僕たちのようなインバウンド対策の企業が出来ることはインバウンド対策におけるテクニカルなサポートです。
既に多くの外国人観光客を抱える地域、これから外国人観光客を誘客していきたい地域、それぞれがその地域の魅力やニーズ、課題をその地域の方々、その地域に深く携わっている方々が正確に認識し、その地域に合った対策を検討し、講じていくことがこれからのインバウンド対策に必要なことだと考えています。