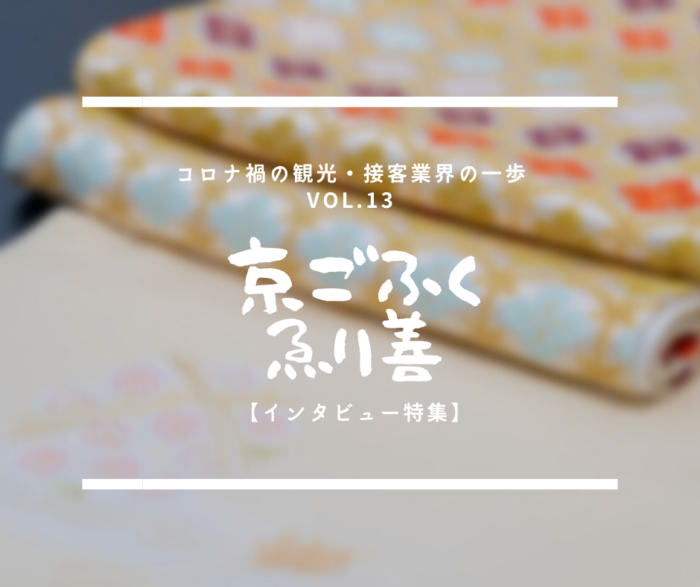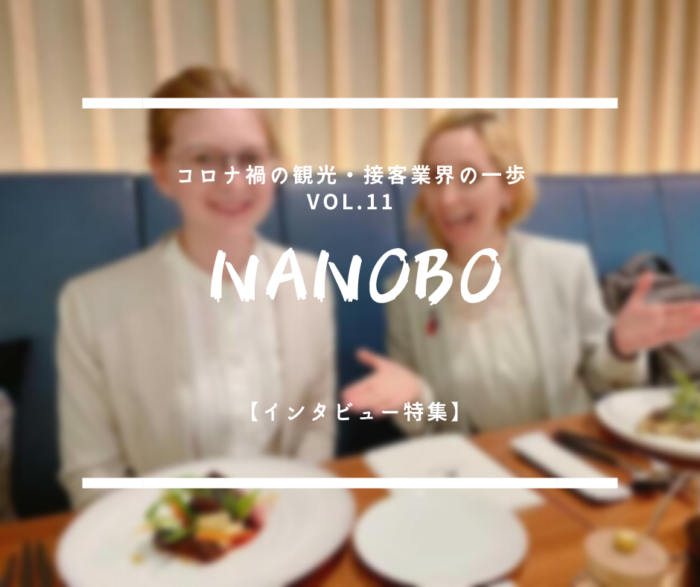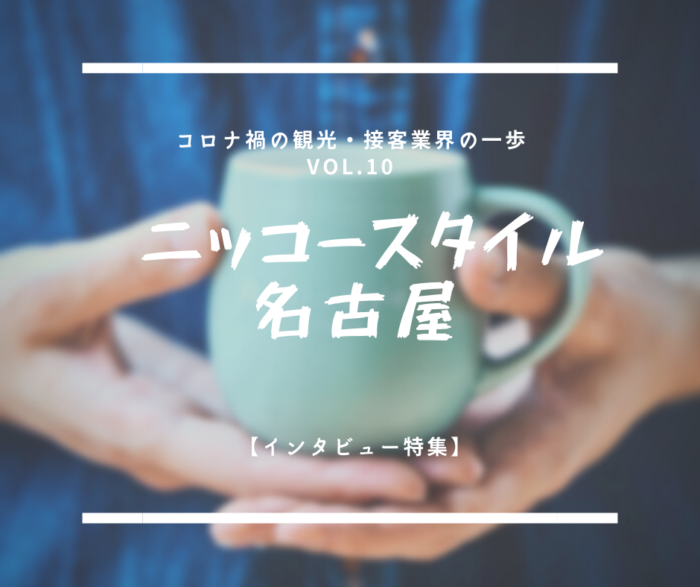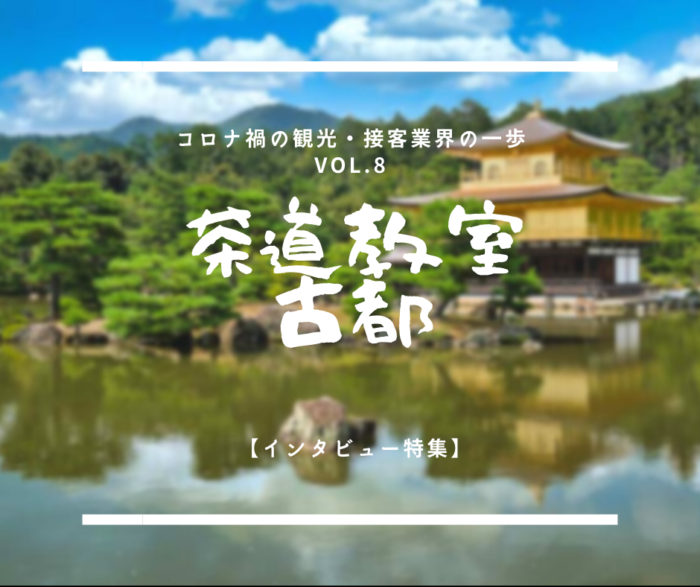この特集にあたって
- 「コロナ禍での観光業界の具体的な状況を知りたい」
- 「観光に携わる方々がこの状況をどのように捉え、動いているのか?」
この記事はそのような方へ向けて書いています。
(この記事は2021年2月10日の取材をもとに作成いたしました)
第七弾は『TSUKIMI HOTEL』
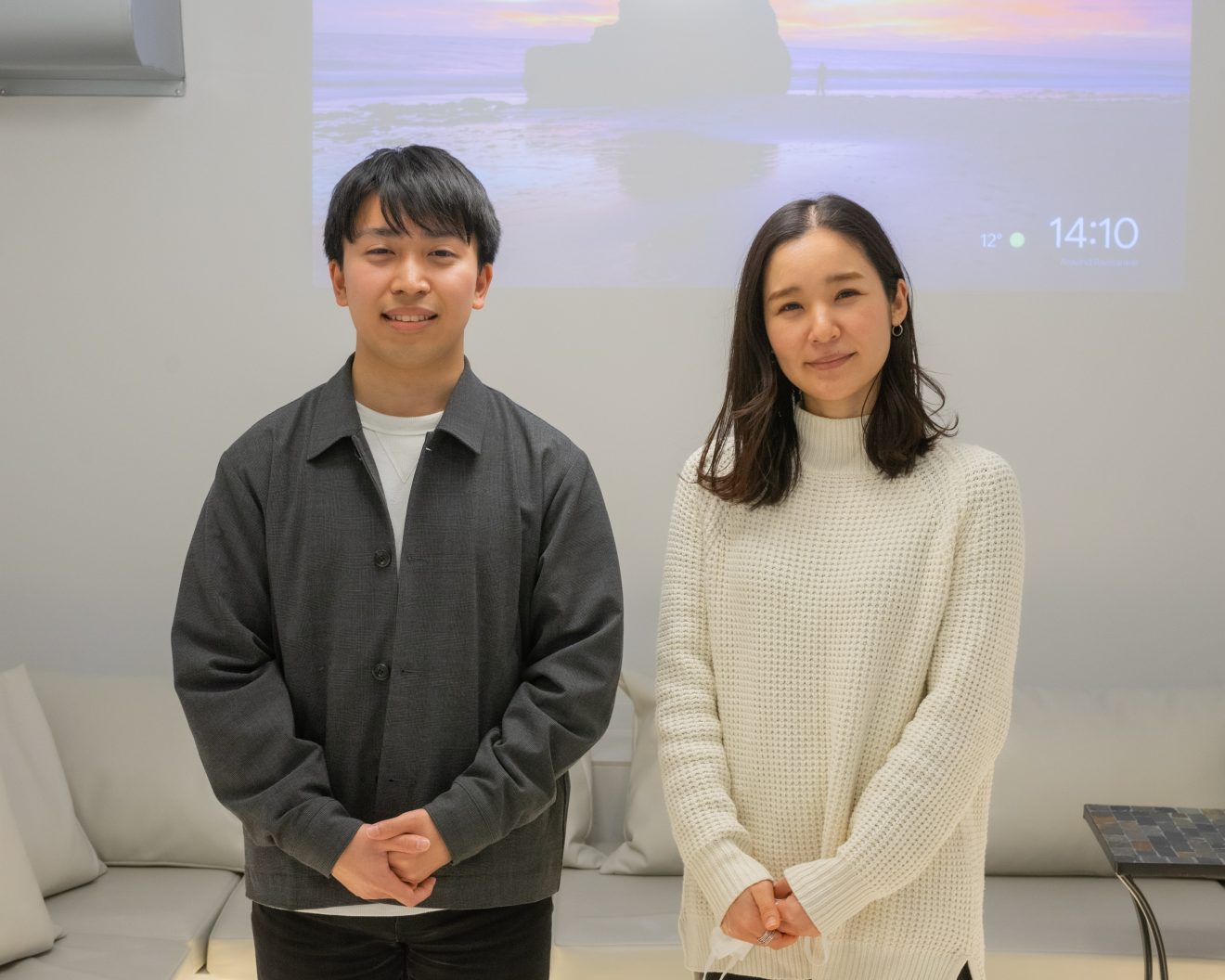
今回は、京都・祇園のカプセルホテルTSUKIMI HOTELさんにお話を伺いました!
TSUKIMI HOTELさんは、「ミニマル」「祇園」「一期一会」をコンセプトに、お客様に最低限で最高品質の宿泊体験を提供しています。
詳しくはTSUKIMI HOTELさんのHPと本記事をご参照ください。
TSUKIMI HOTELさんのHPはこちら↓ https://tsukimi-hotel.com/
祇園で旅人たちを出迎えてくれるTSUKIMI HOTELさんに、コロナ禍での状況や取り組みについてお聞きしました!
プロフィール
エントラスト合同会社
CEO 入柿未来
1、TSUKIMI HOTELさんについて

-TSUKIMI HOTELさんがどういったホテルなのか教えてください!
当ホテルは、インバウンドの方をターゲットとしたカプセルホテルです。
元々インバウンドの方の旅行の仕方に私自身共感しておりまして、その中でお高めな価格の旅館さんが多いこの祇園でも、インバウンドの方の旅行スタイルに合うようなカジュアルに泊まれるホテルをつくりたいという想いから立ち上げることになりました。
特徴といたしましては、最低限・高品質を表す「ミニマル」、圧倒的な立地である「祇園」、ゲスト同士のコミュニケーションやゲストと従業員のコミュニケーションを大事にしたいという「一期一会」をコンセプトに設定しています。
-インバウンドの方の旅行スタイルに共感しているとのことですが、インバウンドの方は実際どのように旅行をしているのですか?
主に欧米の方のインバウンドの話なのですが、清水寺→二年坂→八坂神社などとルートを決めて旅行するのではなく、なんとなく目的を1つ決めて歩く方が多いです。
例えば、京都に3日間滞在する中で、気が向いたところや知り合った人にお話を聞いて良さそうなところに行ってみる。その中でお地蔵さんを見たり苔を見たりして、「あ、京都だ」って感じながら歩かれているんですよ。
また、旅全体の期間は設定しつつも滞在場所をその都度決めている方も多く、最初は2泊で予約していた方が延泊延泊で2週間泊まられて、その1週間後にまた泊まりにきてくれるなど、自由な旅行を楽しんでおられました。
ホテル側としても、これらの旅行スタイルはとても面白いと感じますね。

-コンセプトである「ミニマル」について、詳しく教えてください!
先ほどのインバウンドの方の旅行スタイルと関係しておりまして、目的をなんとなく1つ決めておいて目いっぱい歩き回るインバウンドの方にとって、ホテルに求めているものはなにより睡眠の質であったり快適さだと思うんですよ。
そのため、館内を構成するものの質が非常に大切だと思いまして、カプセル自体を既製品ではなく木で一から組んでつくったものにし、ベッドも海外の高級ホテルさんが利用している「サータ(Serta)社」のマットレスを入れているんです。
そして、高品質のものを必要な分だけ揃えているので、いらないものは省く。この考えが「ミニマル」というコンセプトの根底です。
2、TSUKIMI HOTELさんのコロナ禍の状況と大規模な設備投資

―コロナ禍の状況について教えてください。
昨年の2月まではほぼ満床でしたが、3月には全部屋中10%~15%ほどになり、3月末には4月以降の予約を受付停止しました。
同時に私たちのホテルは国内に強くないので、国内向けのプランを新たに作り、国内に向けた動きをしました。
しかし、5月に入っても3月並みで、人件費を考えると営業している方がマイナスだったので本当にしんどかったです。
7月頃からGoToトラベルが開始しますが、割引比率の高く普段泊まらないような中・高価格帯のホテルに集中してしまい、私たちには恩恵がほとんどありませんでした。
11月は繁忙期なこともあって満床になったのですが、その後の感染再拡大でまた1桁台まで落ち込みましたね。2回目の緊急事態宣言も出まして、現在は予約に応じて開けている状況です。

-先ほど質のいいものを揃えているとおっしゃっていましたが、感染症対策で「新幹線並み」の空気清浄設備を導入したという話が多くの方に注目されています。この設備について詳しくお聞かせください。
元々カプセルホテルなので、一般的な空気清浄機を全ての階に設置するなど衛生面に気をつかっていました。
しかし、コロナウイルスが猛威を振るう中でカプセルホテルの事業形態を変えずに運営していくとなったときに、最低限のレベルではなく、新時代に備えられる徹底した衛生環境を形成することがベストだと考え、今回設備を導入することになりました。
この設備は密閉空間の中でも外気を取り入れ、温度と湿度を管理することができます。
新幹線や飛行機にも採用されているんですけど、これらって窓が開かないじゃないですか。この密閉状態ってカプセルホテルと近しいところがあるので、あの四角い箱の中で温度を調整し、湿度も快適に保つことができるというのは、お客様にも安心していただける要素になると思います。
そのほかにもオゾン発生器やUVライトを導入するなど、感染症対策にかなりの力をいれています。
-投資コストが非常に大きいと思うのですが、どうしてこの選択に踏み切ったのですか?
やはり今は「目に見えて安心できる空間」をつくることが第一だと考えました。
投資コストもそうなんですが、機械自体も本当に大きくて正直ひるみました(笑)。 しかし、可視化できるということは安心感に変わると思うんです。
ですので、この設備にあわせて温度や湿度、CO₂量が測定できるCO₂探知機を導入し、プロジェクターに映し出したりするなど、見える化を徹底しております。
3、「つきみ受験」とTSUKIMI HOTELさんのこれから

-コロナ禍での舵取りはとても難しいと思いますが、コロナ禍ではじめた取り組みなどはありますか?
現在「つきみ受験」といって、京都の大学を受験される方を対象に、無制限完全無料で宿泊体験を提供しております。
実際、色々な方に利用していただいておりまして、北海道からのお客様もおりましたし、京都市内に住んでいる方が自転車で来られて「ちょっと3泊します」みたいな方もいらっしゃいました。
気分転換したい方にも、親御さんが経済的に少ししんどいという方にも提供できればいいなと思っていたので、様々な用途で利用していただいております。
―色々な学生さんとコミュニケーションできて楽しそうですね!
そうですね、ただ受験期の方々はものすごくセンシティブになっていらっしゃいます。
大学生のアルバイトにヒアリングしたときにも、大半が「ほっといてほしい」という意見だったので、必要最低限のことをするだけで、お客様とのやりとりは公式LINEでするようにしています。
例えば、受験生の方から「1時間後とかに夜ご飯お願いします」ってLINEがきたら準備しておいてあげるなどしています。
受験生の方にも、勉強用に貸しているマットレス無しの部屋で黙々と勉強したり、ちょっと散歩に出かけたり、屋上で勉強したりと、自由に利用していただいております。
勉強が終わってからLINEくださる方や、こんなところが良かったなど色々連絡くださる方はいらっしゃるのですが、滞在中のコミュニケーションは空気を読むようにしています(笑)。
「つきみ受験」の詳細はこちらです↓
https://tsukimi-hotel.com/wp/blog

-まだまだ余談は許されない状況が続いておりますが、コロナ禍で取り組もうとしていることはありますか?
TSUKIMI HOTELの運営会社である「エントラスト合同会社」が主体となって、京都の魅力発信に力を入れております。
具体的には、「京都の助け合いの輪」という補助金制度を活用して、京都の企業20社ほどで海外向けの動画を制作するプロジェクトを進めております。
京都は言わずと知れた観光都市で、日本国内外から多くの関心が寄せられていました。しかし、コロナ禍で生活が変化し旅行がままならなくなった今、観光する側はあまり京都のことを気にしなくなりました。
一方で、京都には観光業で生活している方が沢山います。そこで、「京都にはこんな場所があるよ!」「京都にはこんな企業さんもいるよ!」と国内外問わず発信することで、京都が今も動き続けていることを多くの方に伝えようということで、このプロジェクトが始動しました。
そして、このプロジェクトでつながった企業様方と提携し、体験型の旅行プランをつくるなど、未来に向けた取り組みも進めていこうと思っております。

―最後に、TSUKIMI HOTELさんの今後の展望を教えてください!
お客様に戻ってきていただけるのが前提のもと、もう少し国内の利用者様の比率をあげることで、インバウンドの方と現地の方との交流が生まれるようにしたいと考えております。
インバウンドのお客様が日本の色々な場所から泊まりに来ていただいたお客様と交流し、それを参考に次の目的地を決める。
このような展開をつくれると面白いホテルになるんじゃないかなと思っています。
中井の一言コメント
今回インタビューを通して、TSUKIMI HOTELさんが徹底している「目に見える安全」の提供や、空間内の細微に至るまでの工夫を知ることができ、TSUKIMI HOTELさんの提供する居心地の良い空間が生まれる秘密を覗かせていただきました。
また、インバウンドを中心にしていたところからの方針転換や社会貢献には見習うべきところが沢山ありました。
入柿様、この度は取材に応じてくださり本当にありがとうございました!