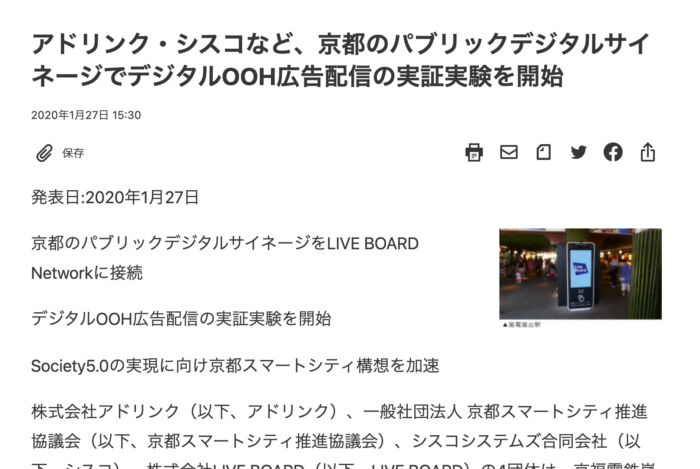日本政府は東京オリンピック以降の経済成長をカジノに期待するという構図になるわけですが、ラスベガスやマカオ、シンガポール等カジノが経済の中心となっている先達の事例からカジノの現状を見ていきましょう。
他国のカジノ売上の推移

まず、代表的なカジノの売上の状況について見てみましょう。 日本にカジノが出来た場合、地理的にはライバルとなりそうなマカオ、シンガポールの状況とラスベガスの状況を確認しましょう。
マカオ

マカオ政府の発表によると2017年の賭博業収入は約3兆7000億円で前年比19%の増加となりました。 中国政府の反腐敗運動の緩和や運営会社の施設充実策や一般客の誘致強化が実を結んだ形です。 しかし、業績を大きく左右する中国人富裕層のマカオを敬遠する傾向は続いています。
シンガポール

シンガポールのカジノ2社の2017年度の売上高は5,383億円、前年の4,861億円を上回る結果となりました。 2010年のカジノ解禁から一時はラスベガスを超える売上となったものの、その後は低迷していたところが2017年は一息ついたというところです。 要因はマカオとほぼ同じと推察され、中国人富裕層頼みという側面が浮き彫りになった形です。
ラスベガス

ラスベガスの売上は2015年の9,617億ドルから2016年の9,713億ドル、2017年の9,978億ドル(1兆997億円)と直近の3年間は微増を続けています。 2017年10月の銃乱射事件が記憶に新しいところですが、客足はすぐに戻ったという情報もあります。
カジノ設立での懸念事項

カジノ法案についてはデメリットとして挙げた項目が議論の対象になりがちですが、そもそもカジノを設立する目的についての懸念があることを忘れてはいけません。
①インバウンド人口の目標・2030年6000万人を実現できるのか?

インバウンド人口は年々増加しており、東京オリンピックが控える2020年の目標は4000万人となっています。 さらに2030年の目標は6000万人となっており、これを達成するためには10年連続で5%の伸びを維持する必要があり、これをカジノが集客の中心的な存在を担って牽引するという構図ですが、容易なことではありません。
②期待されるだけの売上達成できるのか
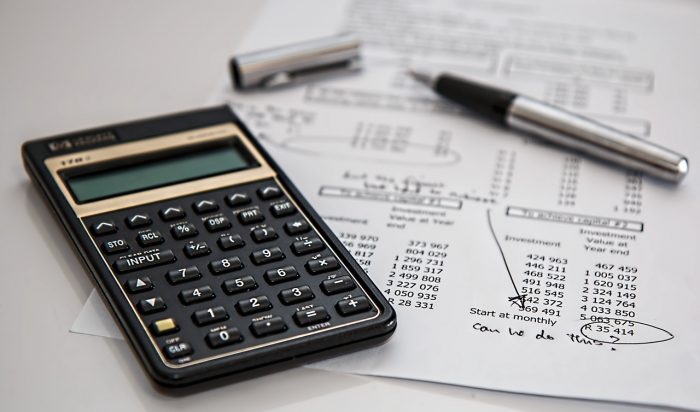
以前、経団連が行った試算によると、統合リゾート施設1カ所につき、需要創出効果が年間3千億円、波及効果まで含めた経済効果は6千億円に及ぶとされています。 実際にはシンガポールやマカオとの集客競争が発生することが予想されるため、この試算が妥当であるかどうかは今の段階では未知数です。
③カジノ管理委員会の脆弱性

カジノで日本の経済が活性化する、というストーリーはカジノが公正かつ健全に運営されることが前提となります。カジノの事業免許は、詳細な調査を行った上で付与されることになっていますが、監督には、独立した行政委員会で、国会同意人事で委員を選任する「カジノ管理委員会」があたります。 しかし、管理委員会事務局にカジノ事業者を任用する可能性や職員移動の制限を設けないことなどが提示され、管理・規制を行う組織として実効性があるのかという指摘が行われています。
④依存症の深刻化

カジノのデメリットとしても挙げられているギャンブル依存症問題ですが、日本には建て前上、公営以外のギャンブルは存在していません。しかし、パチンコに熱中するあまり子供を車内に残し熱中症で死亡させてしまう等の事件が象徴するようにギャンブル依存症は社会問題となっています。 統合リゾート施設、という表現はマイルドに響きますが、結局のところ賭博場を作るわけですから更にギャンブル依存症の人を増やすことになったとしても不思議ではありません。 また、国がギャンブル施設を作りながら依存症対策をする、というところに矛盾があるという指摘も無視できないものがあります。
まとめ
カジノによって訪日外国人観光客を更に増加させつつ、周辺の雇用拡大や関連業界の活性化等を含めて大きな経済成長を見込むカジノ法案ですが、メリット以上にデメリットも目立ち、まだまだ解決すべき問題点は数多く残されています。 少子高齢化による人口減少等、内需がシュリンクすることが確実な日本において、観光立国化をこれまで以上に推進する目玉の一つとしてカジノ、という戦略にはまだまだ否定的な声も多く、政府の今後の舵取りを注視していきたいものです。